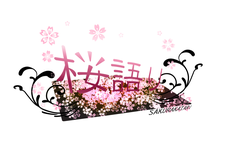七片目:Something unusual
『目的地ニ到着シマシタ。目的地ニ到着シマシタ』
ぱぱらぱっぱぱ〜〜とかいう腑抜けた軽快な音楽と共に、機械がそう報告してくる。
着いたんだ、そっか…ふ、ふふ…死ぬかと思った…。
長い長い溜息の後、俺は座席の背もたれに体を預けたまま目だけを動かす。
看板みたいな物を見つけたので読んでみると、氷室研究所って書いてあった。
へー、氷室……ん?
氷室って俺の苗字じゃん。
もしかして此処って。
『用事を済ませて来る。お前達は待っていてくれ』
酔いも疲れもしていないらしくいつも通りの調子なヴォルクの声が、
ドアの開閉音と同時に聞こえた。
若干遅れてリヴとイリーナの行ってくる的なニュアンスの声が続く。
…あーあ、聞きそびれた。
………実はこの研究所、俺のじーちゃんが所長をしてる所なんだよ。
んでもってじーちゃんが、
優秀な教え子が俺が教える技術をことごとく吸収していくんだ
…って嬉しそうに話してきた事が、昔あった。
その優秀な教え子ってのがヴォルクなんじゃないかなって思ったんだけど。
まあ……いっか。
窓越しに空を眺めてぼーっとしながら、
相変わらず青いなあーとか適当な事を考えていると、大分体力が回復してきた。
気分転換に、ちょっとそこら辺歩こっかな。
サイドカーから降りて一つ大きな伸びをした後、俺は辺りをぐるりと見渡した。
そこでふと、違和感に気が付く。
こんなに死体って少なかったっけ、っていう違和感に。
土に還るには余りにも早過ぎる。
誰かが埋葬でもしてる?んな訳ない。
ケモノは確かに人を喰うけど、こんな塵も残らないレベルで食べ尽くす事はしない筈。
でもケモノの仕業じゃないとすると、一体誰が?
…………………………………。
…………………………考えれば考える程分からん。
一人で悩んでも仕方ないし、語とアリアさんに相談しよう。
ひょいっと車の中を覗き込むと、アリアさんは夢の中に旅立っていた。
語は起きてる。
俺に気付いたらしく、窓を開けてくれた。
「どうかした?」
「ちょっと相談したい事があってさ。そっちお邪魔しても良いか」
「構わないのね」
「サンキュ」
前の座席に二人が座っていたので、後ろの方のドアを開けて中に入り、すとんと座る。
「何の話?」
訊ねられた俺は早速話に入ろうと、単刀直入に言った。
「変な事に気付いてさ」
首を傾げられたので死体の事について切り出そうとした時、語はもしかしてと身を乗り出した。
「サクラも気付いたの?
ケモノが昨日の夜、一匹たりとも現れなかった事」
…………………………………。
……………。
…え?
「どういう事だよ、それ」
俺がそう言うと、語は何だ違うのか…とでも言いたそうな顔で肩を落としてから、
気を取り直した様に俺を見て再び口を開いた。
「どういう事も何も、その通りの意味なのね。昨日ふと目が覚めた時、凄く静かでさ。
いつもなら微かにケモノの足音とかがするのに不思議だなと思って、
見張りに立ってくれてたリヴに、何かおかしくない?って訊ねたんだ」
ふむふむ。
「そしたら頷かれて、全然ケモノが見当たらないって言われたの。
まさかと思って二人でちょっとデパートの中を歩いてみたんだけど…
本当にいないみたいだった」
「…たまたまデパートに出現しなかったんじゃないのか?」
突然パッといなくなるなんておかしいし。
肯定されると思ったけど、語は首を横に振った。
「それが…外も一応見たんだけど、全然見当たらなくて」
ふむ……急に現れて、急に消えて………かあ。
もしかしたら夢だったんじゃ。いや、それはないない。
でも……あの危険生物がいなくなってくれたっていうんなら、嬉しい。
「居るのが当たり前って感じだったからちょっと気になるけど、
まあ結果オーライなんじゃねーか?
出て来たら出て来たで対処すれば良いし」
明るい調子でそう言うと、語は微かに微笑んだ。
「それもそうだね…もう二度と出て来ないと良いけど…」
「フラグっぽい事言わんで下さい」
「すまねえ。
……っと、それはさておき」
頭の後ろで腕を組んでシートに沈み込んだ語が続ける。
「サクラが気付いた変な事って何なの?」
「えっと、あのさ。死体が…」
少なくなってるんだ、と言おうとして止めた。
「ねえ、見て!!」
語がそう叫んだからだ。
指さした方に視線をやると、死体があった。
そこまでは今となっては普通だ。
それが普通なのが如何に異常なのかは今は置いておく。
…………………………………。
やばい、何だこれ。明らかにおかしい。
みるみる内に死体が薄く透明になっていってる。
背景と同化しようとしてる。
………目を凝らしてジッと観察していると、やがて完全に死体は見えなくなった。
まるで最初から、其処に何も無かったみたいに。
「…サクラが言いたかったのって、この事?」
呆然とした顔で語が訊ねて来た。
俺は頷く。
「…うん。まさかこんな風に消えるなんて思っては無かったけど。
やけに死体の数が減ってるなあくらいにしか…」
少しの間の後、俺達は頷き合って車から出た。
さっきまで死体があった場所まで警戒しながら近付く。
「本当に消えちゃってる…」
「……ちんちくりん、あれ…」
思わず言葉を失ってしまった。
比較的近くにあった死体が消えていったから。
辺りを見回すと、他の死体も同じだった。
一つ、また一つと。
…一体何がどうなってんだ。
呆気に取られている間にも、謎の現象は止まることを知らず…
やがて道に転がっていた死体は、一つ残らず消えて無くなってしまった。
目をゴシゴシと擦っても現実は何も変わらない。
若干思考停止し掛けてると、声がした。
「何を突っ立って居るんだ、そんな所で」
ヴォルクだ。
振り向くと、彼は不思議そうな顔で俺達を見ていた。
いや、俺達というかはその周りって感じだな。
「こんなに殺風景だったか…?」
呟いたヴォルクに、俺は訊ねる。
「用事は済んだって事で良いのか」
頷いたヴォルクは、何となく清々しい顔をしている様に見えた。
気のせいかな。
ふと視線をヴォルクの後ろにやると、車の近くでリヴがぶんぶんと手を振っていた。
イリーナも居る。
二人共セーラー服に身を包んでるみたいだ。
多分、あれが此処に来た目的の普段着なんだろう。
「よし、じゃあ早い所図書館に行こうぜ」
まだボーッとしてる語の肩を軽く叩くと、ハッとなった彼女は
「うん、そうだね」
と若干ぎこちなく返して来た。
車に向かって歩く俺達の背中に、ヴォルクの声がぶつかる。
「おい、此処らにあった筈の死体はどうした」
ギクゥ!触れるの辞めようと思ってた話題ををを!
え、ええーっと……………………………上手く説明出来る自信が…ない…なー…。
死体が消えたんだよ!スーッと何の前触れもなく!
…こんな感じ?!
うん、ないな!!!
助けを求めるつもりで語を見ると、彼女は任せろ!とでも言う様に軽く自分の胸を叩いた。
数分後。
語の説明のおかげでヴォルクは納得してくれた。
「こんな事態が起こるなんて、何だか嫌な予感がするのね。
これ以上変な事が起きる前に、早い所創造の本を見つけなきゃ」
「だな」
滅亡した事で、徐々に世界がヤバイ方向に進んで行ってるのかも知れないし。
頷き合った俺と語は、ヴォルクの腕を片方ずつ掴んで走り出した。
「おい、何をする!」
走るのが苦手なのか焦った様にヴォルクがそう訴えて来るけど気にしない。
「これから先何か起こるかも知れない以上、時間を無駄に出来ねえじゃん?
急がないと!」
「そうそう!」
「それはそうなのかも知れないが…いや待て!
わざわざ走らなくても先にお前達が車に乗ってだな…!」
あ。
そっか何もこいつまで走らせる必要無かった。
失敗失敗っ☆彡
パッと手を離すと、語も同じ事を思ったのかそうした。
ぜえぜえと荒い息を吐きながらヴォルクは言う。
「全く、気付くのが遅いぞ馬鹿…。車の動かし方は…イリーナが知っている…」
「おっけおっけ。それにしてもお前、よく俺達に近付けたよな」
「100m以内ならちゃんと歩ける」
「運動不足にも程があるだろ…」
ドン引きしている俺の内心を察したのか、ヴォルクは言い訳を始めた。
「研究所に篭りきりだったし、住み込みだったんだから仕方ないだろう。
動く必要が無かったんだ」
「うん分かった。無理すんなよ、引き篭もりのヴォルクさん」
「引き篭もりじゃな………」
言いかけたヴォルクが口をつぐむ。
否定出来ないと思ったんだな…。
何だか可哀想に思えてきた時、レッド号(改)が俺達の横にスッとやって来た。
どうやら語は俺達を置いて一人でさっさと車に辿り着いたらしい。
窓を開けた語が、わざわざ拡声器を使ってこっちにアナウンスしてくる。
『其処の仲良し二人組ーさっさと車に乗りなさーい。
さもなくば置き去りにするのねー』
「別に仲良くねえし!」
『うるっせえツンデレとか求めてねえんじゃ早く乗れ』
「すみませんでした」
サイドカーにすごすごと乗り込むと、ヴォルクがまだ立ったままなのに気が付いた。
窓を開けて俺は訊ねる。
「何してんだよ。本当に置いてかれるぞ」
何故かショック受けてますみたいな目で見られたので首を傾げると、彼は口を開いた。
「サクラは俺が嫌いなのか」
「え?」
……………………………………えー。
好きかって聞かれたら、いや?ってなるけど、
嫌いかって聞かれたら、そうでもないってなる。
という訳で俺は答えた。
「別に嫌いじゃないけど」
それで丸く収まるかと思ったら、ヴォルクはまた訊ねてきた。
「じゃあ何故仲良くないと言ったんだ」
ちょ、おま…そういう事聞く?聞いちゃう?
察して下さいよ天才なんでしょうが!
ああでもこの人今まで友達いなかったんだった…期待するだけ無駄か…。
…………………………仕方ない!腹をくくれ俺!
「単純に恥ずかしかっただけです!!」
納得しろ!
さあ早く!
「は?」
てめこのこいつううううううううううううう!!!!!
きょとんとすんなよ気付けよお~~~~~~~!!!!
「だ、だから!仲良いって茶化されたのが照れ臭かったからつい強がっちゃったてへ!
ってだけの話なんだっつの!!語もツンデレ云々言ってただろ!?」
「そうなのか…何故お前がツンドラになったのかは分からないが、そういう事か…」
「待てツンドラじゃねえよ。人間じゃなくなってんじゃねえかおい」
俺の訂正が届いているのかいないのか、
ヴォルクはやたら嬉しそうにテクテク歩き出して、さっさとサイドカーに乗り込んで行った。
はあやれやれなんかやたら疲れたぞ…手間の掛かる友達を持つと大変だなあ…。
元々レッド号に付いていたらしいカーナビ機能で最寄りの図書館を見つける事が出来たので、
其処に行く事が決まった。
夕日が昇り始める。
その眩しさに目を細めながら、ぼけーっとケモノ出てくんのかなあなんて考えた。
出て来たらそりゃ迷惑だし嫌だけど、
居なくなったらそれはそれで物足りないというか、不気味というか。
そんな事を考える余裕があるなんて、我ながら慣れたもんだと思った。