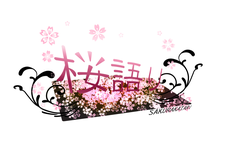幕間4
氷室研究所。
俺が住み込みで研究に明け暮れた場所。
人生で一番長い時間を過ごした、思入れのある場所。
一部倒壊はしていたものの、幾つかの部屋は無事だった様だ。
見慣れた廊下を歩き、突き当たりにある自室を目指す。
…早くロボットを確認しなくてはいけない。
サクラ達にはリヴとイリーナの服を取りに行くだけだと予め伝えてある為、
馬鹿みたいに時間が掛かってしまっては怪しまれるだろう。
ロボットを確認したい、とは言えなかった。
もしもの事を考えたら、怖くて。
俺のロボットがあの変な生物だった場合。
あのメンバーの中に、それによって大切な誰かを失った者が居たとしたら。
…………そう考えると、口が裂けても本当の目的は言えなかった。
進んで行く内に、教授の部屋を通り過ぎた。
此処の所長であり、俺の恩師。
リヴとイリーナを作って間も無い頃、俺の大学に来ないかと誘ってくれた人。
色々と世話を焼いてくれた。
面倒を見てくれた。
俺は彼を、父親の様に思っていた。
彼も俺を、自分の子の様に感じていると言っていた。
教授は昔、当時6歳だった息子を交通事故で喪ったのだと言う。
しかし不思議な事に、その子の死体は見つからなかったのだそうだ。
事故に遭った所を見たという人達は、口を揃えて忽然と消えてしまったと言ったらしい。
教授は、この目で見ないと諦め切れない、
それにもしかしたら生きているのかも知れないと必死になって、
息子…すずろを見つけようと世界中を探し回ったのだという。
彼が俺と出会ったのは、教授の妻である女性が急病で亡くなったという事を
すずろより3歳年下の娘…朱櫻から聞き、
彼女を一人にする訳にはいかないと旅を諦めて帰る最中だったそうだ。
教授は今、どうしているのだろうか。
どうか…無事であって欲しい。
「はかせ、着いたわよ!」
リヴの声にハッとなる。
「もー!周りが見えなくなるくらい考え事に没頭するのって、本当はかせの悪い癖かしらー」
すまないと一言謝罪してから、俺は自室のドアを見た。
指紋認証システムで開く仕組みだったが、電気の供給が止まっている今…。
「力づくで開けるしかないですね」
イリーナの言葉に頷くと、リヴが目を輝かせた。
「任せて任せて!バーンっと豪快に開けてあげるかしら〜」
リヴはイリーナと比べて、かなり力が強い。
彼女のエネルギー源が太陽光だからなのか原因は定かではないが…出力の差は歴然だ。
リヴはドアから距離を取り、助走を付けて軽く跳んだ後、両足を扉に叩きつけた。
鈍い轟音と共に、ドアが部屋の中に倒れていく。
宣言通り、何とも豪快に開けてくれたものだ。
「大成功〜!」
ドアもろとも突入していったリヴの明るい声が聞こえる。
どうやら怪我はしていないらしい。
イリーナと顔を見合わせた後、俺は部屋に足を踏み入れた。
真っ直ぐに部屋を進む。
…心臓の鼓動が速くなったのを感じた。
汗が微かに滲む。
奥の扉。
その先にロボットが居なければ終わりだ。
パソコンからノートパソコンに一応移動させておいたロボットのシステムプログラムは、
ロボットが壊れて機能していないからなのか、全く使い物にならなかった。
でもそれが、機能していないからではなく、暴走しているからだったとしたら。
扉を開けるのが、怖い。
もしロボットが原因だったとしたら。
それであいつらが誰かを失っていたとしたら。
俺は何も知らないフリをして、あの中に居られない。
知りたくない。
このまま、リヴとイリーナの服だけ回収して戻ろうか。
ああ、その方がきっと良い。
知らない方が幸せな事だってある。
……………………………旅を、続けたい。
「はかせ」
踵を返そうとしていた俺を、イリーナが呼び止めた。
左右で色の違う瞳が、真っ直ぐに見つめてくる。
「逃げちゃ駄目なのです」
黙り込む俺の手を両手で包んだイリーナは、静かに続けた。
「怖いのは分かります。
だけど、私は確かに貴方に言った筈ですよ」
思い出して下さいと優しく言われ、昨夜の彼女の言葉が蘇る。
『結果がどうあれ、私は…私達はずっと、はかせの味方です。
はかせが悪事を働こうとしていなかった事は、リヴと一緒に誰よりも近くで見ています。
もしロボットの事ではかせが責められる様な状況に陥ったとしても大丈夫です。
絶対皆さんを説得して見せるのです』
…………そうだ、イリーナはそう断言してくれた。
俺が思い出した事を察したらしく、彼女は芯の通った声で言う。
「貴方の旅を、貴方の幸せな時間を…絶対に守ってみせるのです」
俺達のやり取りを優しい眼差しで見守っていたリヴが、口を開く。
「逃げても、もやもやするだけだもんね。
新しいスタートとして一歩踏み出しましょ、はかせ!」
……ああ、なんて頼もしいのだろう。
昔から、ずっとこうだ。
俺が悩んでいる時、こうして二人は背中を押してくれる。
そしてその後、隣を歩いてくれる。
無くてはならない…大切な、家族。
もう、大丈夫だ。
何も案じる事なんて無い。
「…有難う。一緒に、来てくれるか」
「勿論よ!」
「何処までも、お供するのです」
俺はもう一度礼を言ってから。
意を決して、ドアノブを握った。
部屋を巡回した後。
思わず体から力が抜け、俺はその場に座り込んだ。
「良かったですね、はかせ…!」
「これで安心ね!」
二人の嬉しそうな声に、ただただ頷いた。
ロボットは、収納されたままだった。
一体も欠ける事なく、変わらぬ姿で機能を停止させていた。
俺のロボットは、何もしていなかった。
嬉しさと安堵が胸に広がる。
視界がぼやける。
行き場の無い気持ちが、呻き声になって現れる。
声にならない。
イリーナに優しく抱き締められ、流れる涙をリヴに拭われながら、
こんなに泣いたのは何時振りだろうと思った。
暫くして、ゆっくりと立ち上がる。
「さあ帰りましょ、はかせ!皆の所へ!」
泣き止んだ俺に、リヴがそう言ったからだ。
帰る事が出来る。
たったそれだけの事なのに、幸せで堪らない。
胸を張って、帰ろう。
リヴとイリーナの服を回収し、馴染みのある服装になった二人と共に研究所を出た。
車にはアリアしか居なかった。
周囲を見渡すと、少し離れた場所にサクラと語が立って居た。
あんな所で何をしているんだ…仕方ない、呼んで来るか。
リヴとイリーナに行って来ると声を掛け。
友人の元へ行くべく、俺は足を踏み出した。