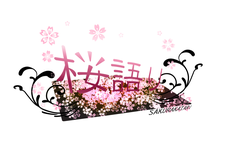幕間3
ロボットに設定した時刻になると出現する、見覚えのある姿。
あの化け物は、俺の作ったロボットなのだろうか。
そんな疑念に駆られ、あれを目撃した時から眠れなくなった。
だが、あんなにも悪趣味なデザインにはしていなかったし、
人を襲う様に…ましてや喰らう様になんてプログラムはしていなかった。
あれは別物なのだろうか。
それとも、俺のロボットなのだろうか。
もし後者なのだとしたら、どう責任を取れば良いのだろう。
世界を滅ぼす要因の一つになった事は間違いない。
あれは数多の人間を殺したのだから。
隕石だけなら復興出来たかもしれない。
しかし復興は人手が無ければ話にならない。
その肝心な人手を、ロボットが根こそぎ奪ったのだとしたら…。
考えただけで、恐ろしかった。
近々、研究所に戻る事が出来る。
そうすれば真実が明らかになる。
ロボットの残骸が研究所に無ければ、
あの化け物は間違いなくロボットの末路だと確定する。
しかし、ちゃんとあったのならば。
ロボットと化け物は無関係だという事になる。
このまま白か黒か分からずに苦しむくらいなら、はっきりさせた方が良い。
先程作った精神安定剤のおかげか、あの声は今は聞こえない。
瞼を閉じても、充血した目は見えてこない。
静かな夜を過ごすのは、随分と久し振りな様に思える。
今なら眠っても大丈夫なのでは無いかという錯覚すら覚えた。
だが、意識を手放すには至らない。
何をするでもなく朝を待つというのは、中々に苦痛だ。
壁に寄り掛かったまま首だけを動かす。
瓦礫の隙間から差し込んでいる月明りの下で、イリーナが座り込んで居るのが見えた。
イリーナの動力は月の光。
だから三日に一度、こうして月光浴をする。
視線に気が付いたのか、イリーナは此方を見て照れ臭そうに微笑んだ。
その後、遠慮がちに手招きしてくる。
話し相手が欲しかったので、俺は寝ている皆を起こさない様にそっとイリーナに近付いた。
「眠れないのですか、はかせ」
腰を下ろした俺に、そっと彼女が訊ねてくる。
頷くと、彼女は悲しそうな顔で、そうですか…と呟いた。
少しの間の後、イリーナが口を開く。
「はかせ…リヴがいなくなったあの日から寝ていませんでしたよね」
どきり、と心臓が鳴った。
「原因は考えなくても分かります。
はかせが研究所に行こうとしている理由も、大体予想出来ています」
続けられた言葉に、胸の鼓動が速まるのを分かった。
何も言っていないのに、全てお見通し。
イリーナは察しが良い。
彼女に隠し事は通用しない。
何処まで知っているのか、気付いているのか…きっと、全部分かっているのだろう。
「結果がどうあれ、私は…私達はずっと、はかせの味方です。
はかせが悪事を働こうとしていなかった事は、リヴと一緒に誰よりも近くで見ています。
もしロボットの事ではかせが責められる様な状況に陥ったとしても大丈夫です。
絶対皆さんを説得して見せるのです」
芯の通った力強い瞳。
それに射抜かれながら、そう励まされる。
「だから、あまり気に病まないで下さい。はかせは悪くないのですから。
そして…一人では、ないのですから」
それからイリーナは、そっと俺の腕を引いて、自分の膝の上に頭を乗せるようにと示してきた。
「精神安定剤を飲んでいるでしょうし、きっと眠っても大丈夫です。
壁に寄りかかっても疲れは取れません。私の膝で良ければお貸しするのです」
…少し気恥ずかしさを感じたが、それもそうだと思い大人しく従った。
イリーナの手が、俺の頭を撫でる。
この年になってまでこんな事をしてくれるのは、彼女とリヴだけだ。
「何だか、昔を思い出すのです」
イリーナの呟きに、そういえばこんな事があった、と思い出す。
研究所に就職して、部屋を貰った初日の事だった。
これからの生活に不安を感じて眠れずに居た俺に、イリーナが今の様に膝枕をしてくれて。
優しく、撫でてくれた。
…あの時も、安心感と心強さに満たされた気がする。
「…良かったですね、はかせ。お友達ができて」
俺は目だけを動かした。
暗がりの中、サクラが寝ている姿が見えた。
…俺の、友達。
初めてリヴやイリーナ以外とくだらない話をした。
好きな食べ物や嫌いな食べ物。
幼児ですら当たり前にした事があるであろう話。
でも、それすら俺は他人とした事が無かった。
あいつは笑っていた。
俺の言葉で、笑っていた。
とても、嬉しかった。
…楽しかった。
「家族である私やリヴでは味あわせてあげられない、友達としての喜び。
それを彼は、はかせにくれた」
頷くと、イリーナは続けた。
「ずっと、気にしていたんです。
はかせは楽しそうに誰かと歩いている人を、羨ましそうに見ていた事があったから」
「………………お前には隠し事が出来ないな」
軽く笑いながらそう言うと、イリーナは小さく微笑んだ。
中学、高校の勉強を2年で終わらせ、大学に入学した俺は、
当然かも知れないが周りに馴染む事が出来なかった。
何故こんな所にガキが紛れ込んでいるんだろうという視線がまとわり付いてくる感覚は
今でも忘れない。
頭が良いのか、羨ましいな。といった内容の皮肉を、数え切れない程言われた。
そんな俺に
気にする事はない。
君が優秀なのは事実なのだから、胸を張っていなさい。
と大学の教授が、言って下さった。
その言葉を聞いて、そういう他人の反応は気にしなくなった。
だけど。
リヴやイリーナ、俺の事を理解してくれた教授が居るのに、何処か寂しかった。
友達。
それは、長い間手に入れる事が出来なかった、俺が無意識の内に求めていたもの。
周りの環境だけが悪いんじゃない。
俺自身にも原因があると自負している。
………………だからこそ、友達を得られた事が、堪らなく嬉しいと感じた。
いつかサクラに、有難うと伝えたい。
あいつは調子に乗るのだろうか。
それとも驚くのだろうか。
一体どんな反応をするんだろう。
何だか少し、楽しみだ。
そんな事を思いながら俺はゆっくりと瞼を閉じた。
何だかとても心が満たされている。
やっと、ゆっくり眠る事が出来そうだ。
「有難う、イリーナ」
「どう致しまして」
とても優しい声だった。
彼女の顔は見えないけれど、きっと微笑んでいるのだろう。
そんな気がした。