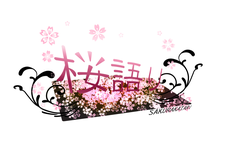幕間2
六月十四日の昼下がり。
平和そのものだった風景が一変した。
炎が、容赦なく住居を、物を…人間を焼いている。
道路がこの場から離れようと必死に足掻く者で溢れかえっている。
メンテナンス中に、猫を撫でてくると言って脱走したリヴの姿は…
この人間の海とでも言うべき道路から、一向に見えない。
名前を呼んでも、悲鳴に掻き消されて埒が明かない。
俺はリヴに埋め込んだ発信機で位置を把握しようと、一旦背後の研究所に戻った。
拉致や誘拐、迷子の対策にと取り付けた発信機が役に立つ日が来るなんて。
そんな事を思いながら愛用している自作パソコンのスリープモードを解き、
アイコンをクリックした。
地図に点が表示されないと言う事は、活動の停止を意味する。
…緊張が走る中、モニターに地図とリヴの現在地を示す、黄色い点が浮かび上がった。
しかし。
ホッとするのも束の間。
点が現在進行形で、研究所から離れて行っている事に気が付く。
リヴは、研究所に俺とイリーナが居ると分かっていて、見捨てて逃げる様な奴ではない。
第三者がリヴを車にでも乗せていると考えるのが妥当と言った所か。
こんな状況で悪事を企む輩がいるとは思いたくない…保護されたと信じよう。
そう結論付けてから、パソコンのデータをノートパソコンに移動させ、カバンに収納した。
…そろそろ、研究所も限界だ。
かなり頑丈なこの建物でも、隕石が降って来るなんて想定はされていなかったのだろう。
直撃した影響からか、先程から建物が微細に震えている。
部屋を出る寸前、俺はある部屋へと続く扉を見た。
俺が中心になって計画や開発を進めていた、
夜間での安全確保を目的とする狼を模した警備ロボット。
数年に渡って試行錯誤を繰り返した…謂わば努力の結晶とも言える、
俺の最高傑作になる筈だった物。
数千、数万の個体が収納されているあの部屋は、
研究所が倒壊するのに伴って確実に潰れてしまう。
ロボットがジャンクになる運命から逃れる事は不可能だろう。
…惜しくはあるが、命の方が余程大事だ。
外に出た瞬間、イリーナが小さく悲鳴を上げた。
地面が死体で埋め尽くされていたからだ。
火事によって黒焦げたものは、元の人間の原型が無く、判別が出来ない。
逃げる最中に転んで踏み潰され圧死したのであろうものは、
手足が不自然に折れ曲がり、口から内臓が出ていた。
まるで、悪夢でも見ている気分だ。
「目を閉じていろ。良いと言うまで、絶対に開けるな」
俺はそう言って、イリーナを抱き上げた。
ある死体の上に足を乗せる。
…人を踏む感触を、初めて味わった。
勿論抵抗はある。
だが、このまま此処に居れば確実に死ぬ。
死体の仲間入りなんて御免だ。
生き延びてリヴと再会する為には行かなくてはいけない。
この屍の上を、歩いて行くしかない。
一歩一歩をゆっくりと進んで行く。
そんな時、足を掴まれた。
「たすけて」
子供だ。
足が潰れただけで死にきれなかったのだろう。
目は見開かれ、充血している。
俺に治療する術は無い。
怪我を治した所で面倒を見る自信も無い。
「…すまない」
手を払う為に、足を動かす。
目を逸らす。
手は力なく空を切った。
子供の顔を再び見る勇気は無かった。
何か別の事を考えていないと気が狂いそうだ。
『たすけて』
さっきの子供の声が頭に響く。
俺が見捨てた。
見殺しにした。
「はかせ」
イリーナが、目を瞑ったまま、話し始める。
「はかせが悪いのではないのです…あの子を助けた所で、無駄に期待させてしまうだけ…。
もしあの子が親を失っていたとしたら、一人で生きて行かなくてはいけません。
今後復興が可能かも分かっていないこの状況で、過酷な生活を強いるよりは…」
言うか言うまいか悩んでいるのか、少し間があった。
「仕方がないのです。残酷な事を言っているのは自覚しています…でも。
あの子一人を助けてしまえば、他の人も助けなくてはいけません。
そうしないと居られなくなる。そうじゃないと潰れてしまう…そんな気がするのです」
少しでも現実から意識を逸らしたかった事もあり、彼女の言葉に意識を集中する。
「誰かの人生を背負う事が出来る人は、極々少数でしょう。
誰かの運命を変える権利は、誰にもありません。だから気に病んではいけないのです」
イリーナが、俺の服をぎゅっと握る。
「はかせは悪くない…何も、悪くないのです…」
俺は小さく、声を絞り出した。
「…………有難う」
本当に、この子は優しい。
優しくて、強い。
それに比べて俺の弱い事と言ったら…情けなかった。
あの子供の声が、止まない。
たすけてという声が、四方八方から聴こえる。
頭の中に響き渡る。
幻聴だと頭では理解しているのに止まない。
足を掴まれる感覚があった。
思わず足を凝視する。
手は何処にも無かった。
瞼を閉じると、あの目が浮かび上がった。
何個も、何個も、俺をジッと見つめている。
どうして助けてくれなかったのか。
そう言っている様だった。
せっかくイリーナが励ましてくれたというのに、もう手遅れだった。
やめてくれ、と叫びたい。
だけど、それは駄目だ。
イリーナを不安がらせてしまう。
もう余計な心配は掛けさせたくない。
しっかりしなくては。
それに。
叫んだ所で声が止む事は無いだろう。
この幻覚が消える事は無いだろう。
俺は死体の上を歩き続ける。
焼けた肉の匂いと煙と、幻聴に包まれて。